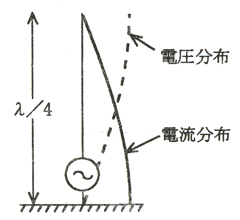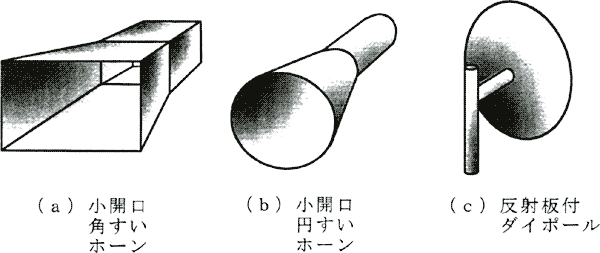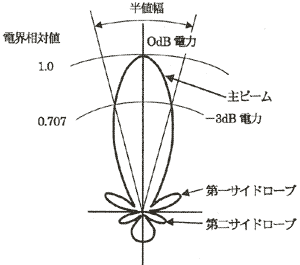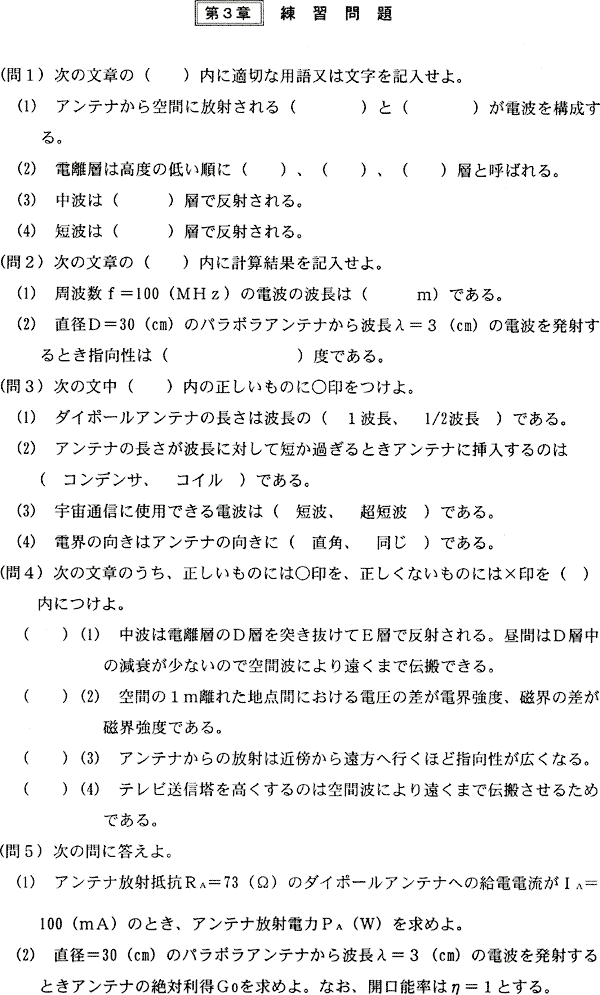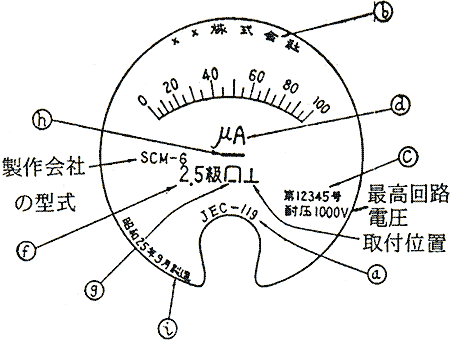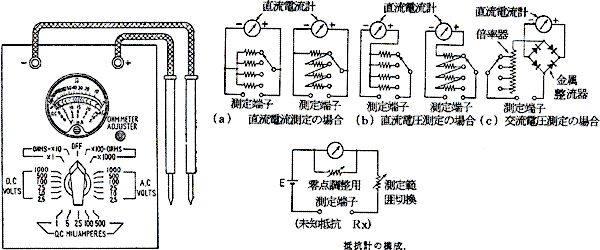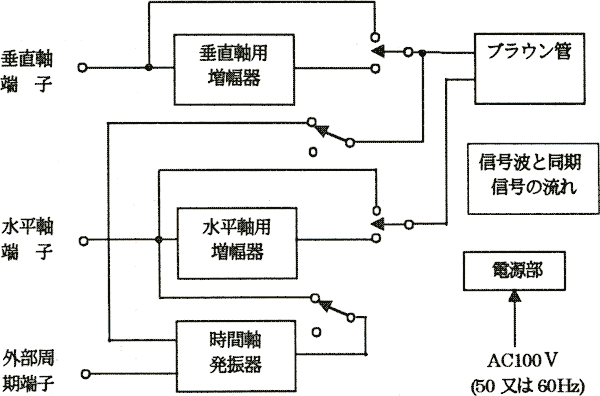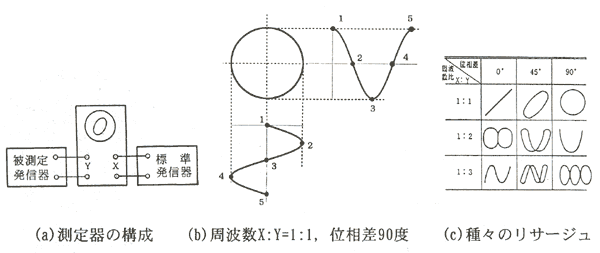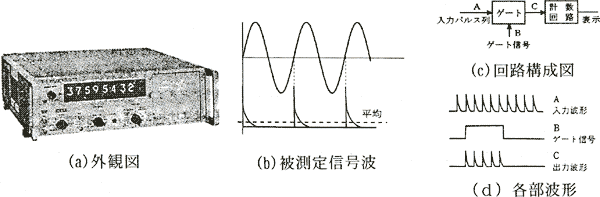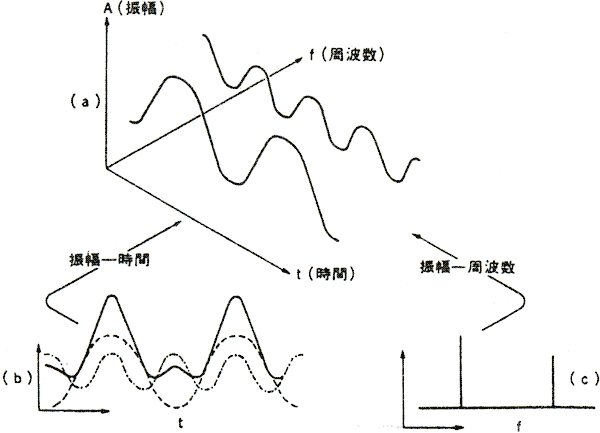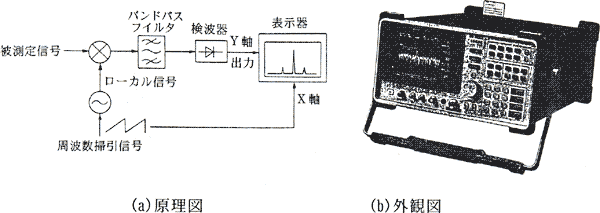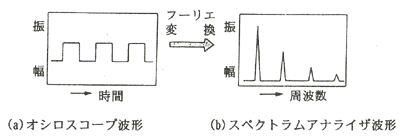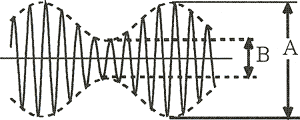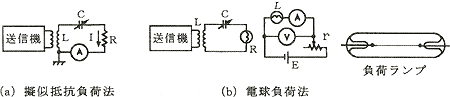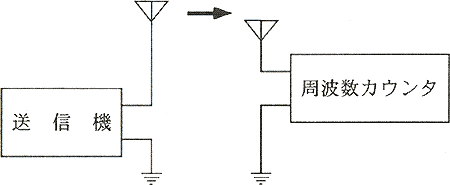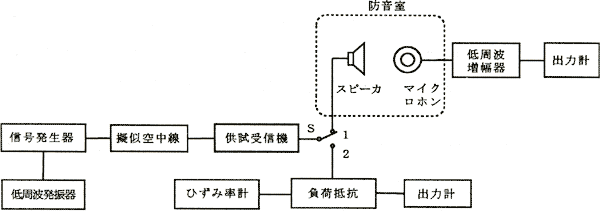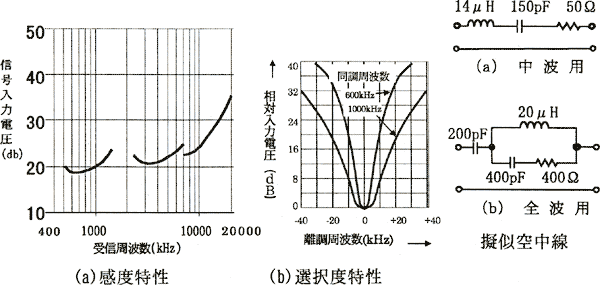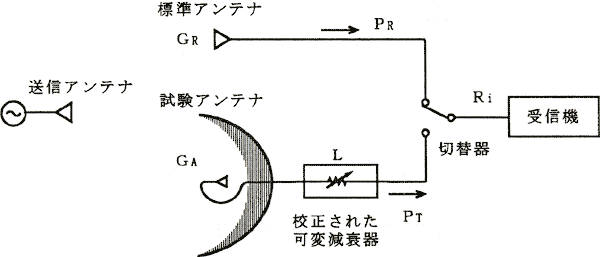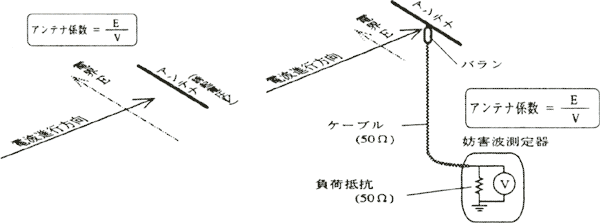|
第3章 電波工学の基礎
3・1 電波とはなにか
3・1・1 電波の発生
アンテナに電流を流すと1・2・2項で説明したように磁力線が発生する。電子と陽子が移動すると電流になることを1・3・2項で説明した。アンテナに電流を流すと図3・1に示すようにアンテナを取り巻く磁力線が発生する。アンテナに電流を流すことはマイナスの電子とプラスの陽子が移動することによるのでアンテナ上の陽子の位置から電子の位置に向かい電気力線が発生して図3・1に示すようにアンテナと同じ方向に電気力線が現れる。アンテナに高周波電流を流すと電気力線と磁力線が電波となって放射される。
図3・1 アンテナ電流による磁力線と電気力線の発生
 送信機から高周波電流を流すとアンテナ電流が周期的に磁力線と電気力線をアンテナから空中に押し出して電波として放射する。電波は電気力線と磁力線が空中を伝搬するので電気磁気波であるが省略して電磁波となり,
さらに短く電波と呼ぶようになった。
アンテナを電波法で空中線と呼ぶ。図3・2に空中線から電気波(電気力線)と磁気波(磁力線)が放射されて伝搬する状態を描いてある。垂直に空中線を置くと電気波は垂直面内を波状に伝搬する。これは電気力線が垂直面内に生じるからである。磁力線は水平面内に生じるので磁気波は水平面内で波状となり伝搬する。電気波と磁気波はお互いに直交した面内に沿って進行する。電波の進行方向に対して電気波と磁気波の振動は横方向となっているので電気的横波とも呼ばれる。図3・2のように電気波が垂直面内にある電波を垂直偏波という。アンテナを横に置くと水平偏波となる。
図3・2 アンテナからの電波の伝搬
 垂直偏波で送信された電波は垂直に置いた受信アンテナで受信する。中波ラジオは垂直偏波で,
テレビとFM放送の電波は水平偏波で送信−受信されている。
図3・3に電波の周波数と波長との関係を示す。
図3・3 電波の波長と周波数の関係
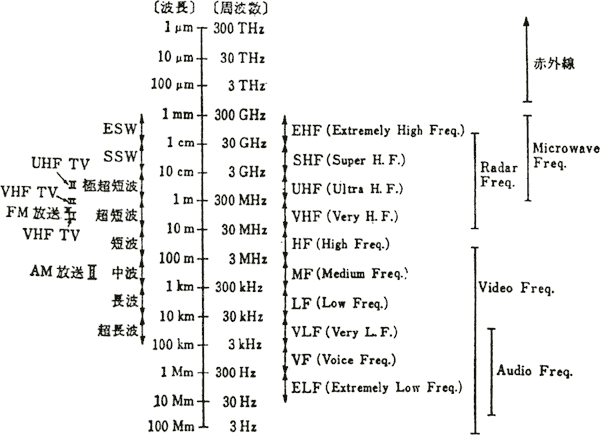 周波数3kHz(波長1000km)の長波から300GHzまでが電波法の対象となるが国際電気通信連合,
ITUにより光や赤外線等の電気振動はすべて電磁波の定義に含まれるようになった。
電波の波長と周波数との関係は
電波の速度C=周波数f×波長λ (3・1)
で計算される。ここで
大気中での伝搬速度c≒3×108 (m/s)
周波数f (ヘルツ, Hz)
波長λ (メートル, m);λはギリシャ語でラムダと読む。
(3・1)式に空中の電波の伝搬速度を代入すると波長は
波長λ=電波の速度c/周波数f
≒3×108/周波数f (m) (3・2)
又は
周波数≒3×108/波長λ (Hz) (3・3)
として計算できる。
例題1.
周波数100(MHz)の電波の波長はいくらか?
解答1.
メガヘルツ(MHz)をヘルツ(Hz)に換算して
100MHz=100×106=1×108(Hz)
(3・2)式より
波長λ=3×108/1×108=3(m),
と求められる。
例題2.
波長2mの電波の周波数はいくらか?
解答2.
(3・3)式より
周波数f=3×108/2=1.5×108=150×106(Hz)=150(MHz)
アンテナから放射された電波は地上波と空間波となって伝搬する。図3・4に電波の伝搬状況を示す。
図3・4 電波の伝搬
  に分類される。
図3・5に電離層と電離層波の伝搬を示す。
図3・5 電離層波の伝搬
 電離層は太陽から放射される微粒子や紫外線により大気中の酸素や窒素等のガスが電離されてプラスとマイナスに帯電したイオンの雲が地球の上空に形成されたもので,
電波を反射したり, 進路を曲げたりして空間波をつくる。高度約50kmのD層は太陽からの紫外線によるもので波長が長い長波を反射する。E,
F層は太陽からの放射微粒子によりつくられる。E層は高度約100kmで中波の進路を曲げて地上に降ろす役目をする。F層の高度は約200kmあり, 昼間はF1とF2に分かれるが夜間に合体して1つの層となる。F層は短波の進路を曲げて地上に降ろす。周波数が高くなるほど高い電離層で反射される。超短波やマイクロ波はすべての電離層を突き抜けるので地上波しか利用できない。
人工衛星は電離層より高い軌道を持つので電離層を突き抜ける超短波やマイクロ波が使用される。より高い周波数のミリ波を宇宙通信に利用すると大気中の雨による減衰が大きくなる。夜間に遠くの中波放送が聞こえるのはD層内の減衰が少なくなり,
D層を突き抜けてE層で反射された中波の空間波が地上に届くから遠くの放送が聞こえるようになる。
|